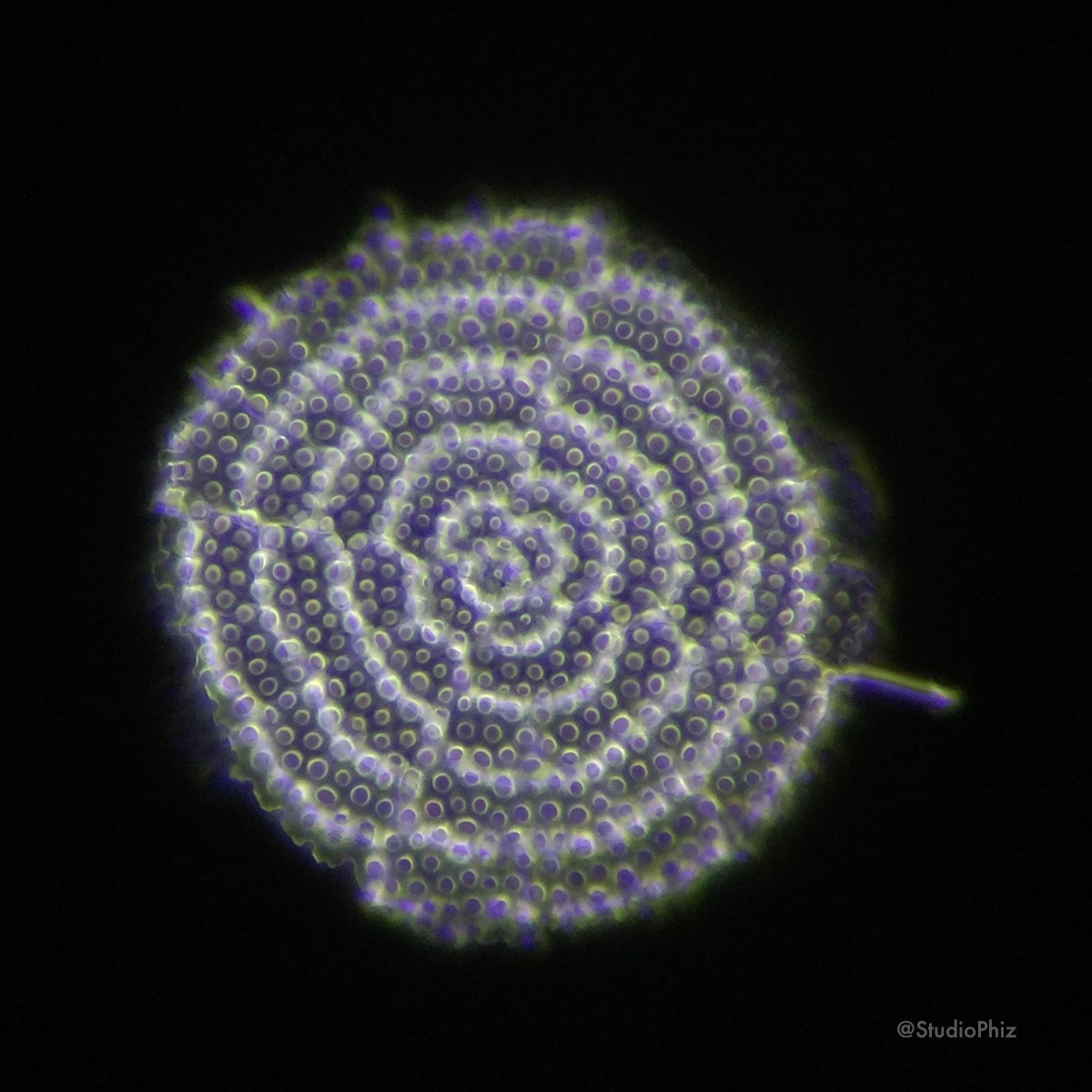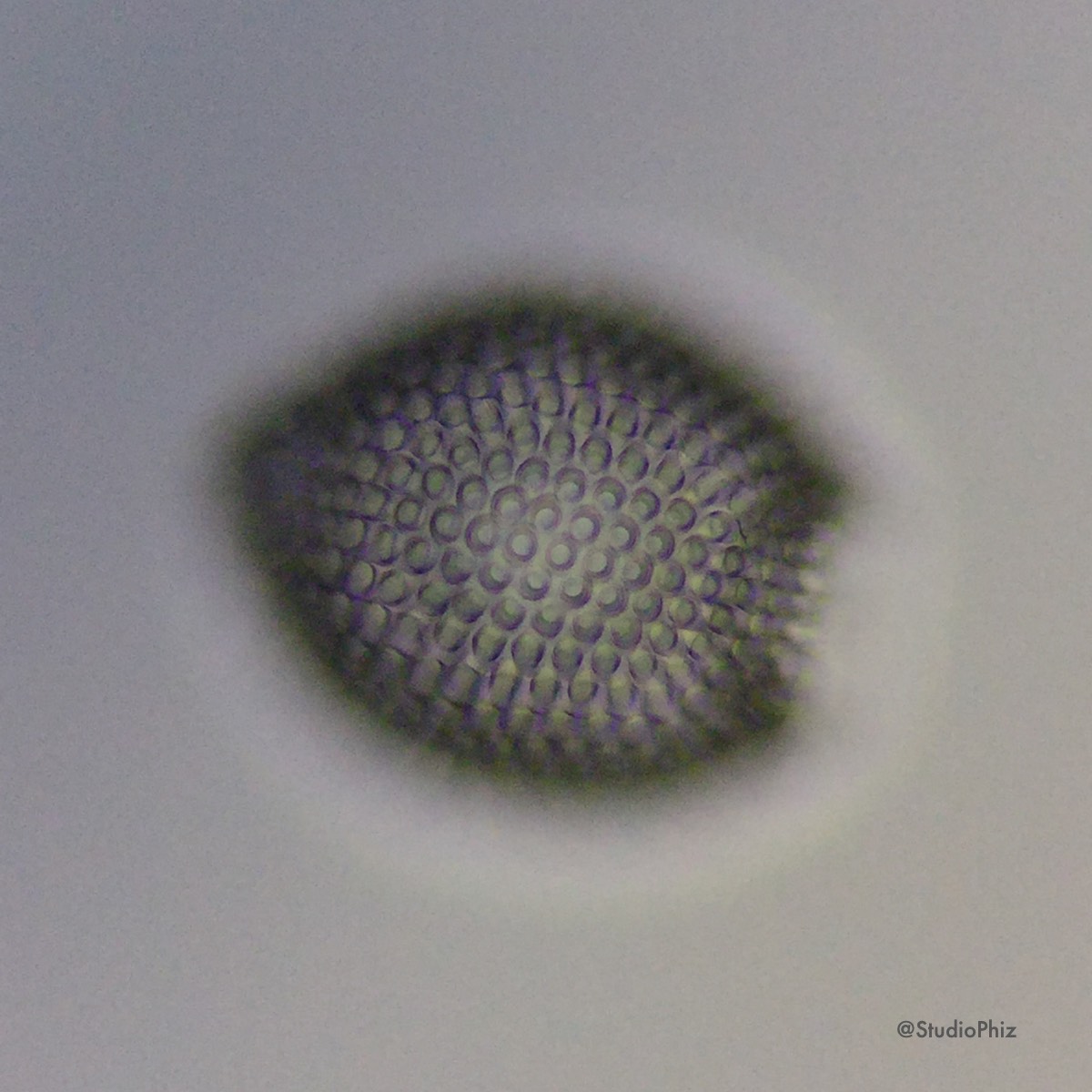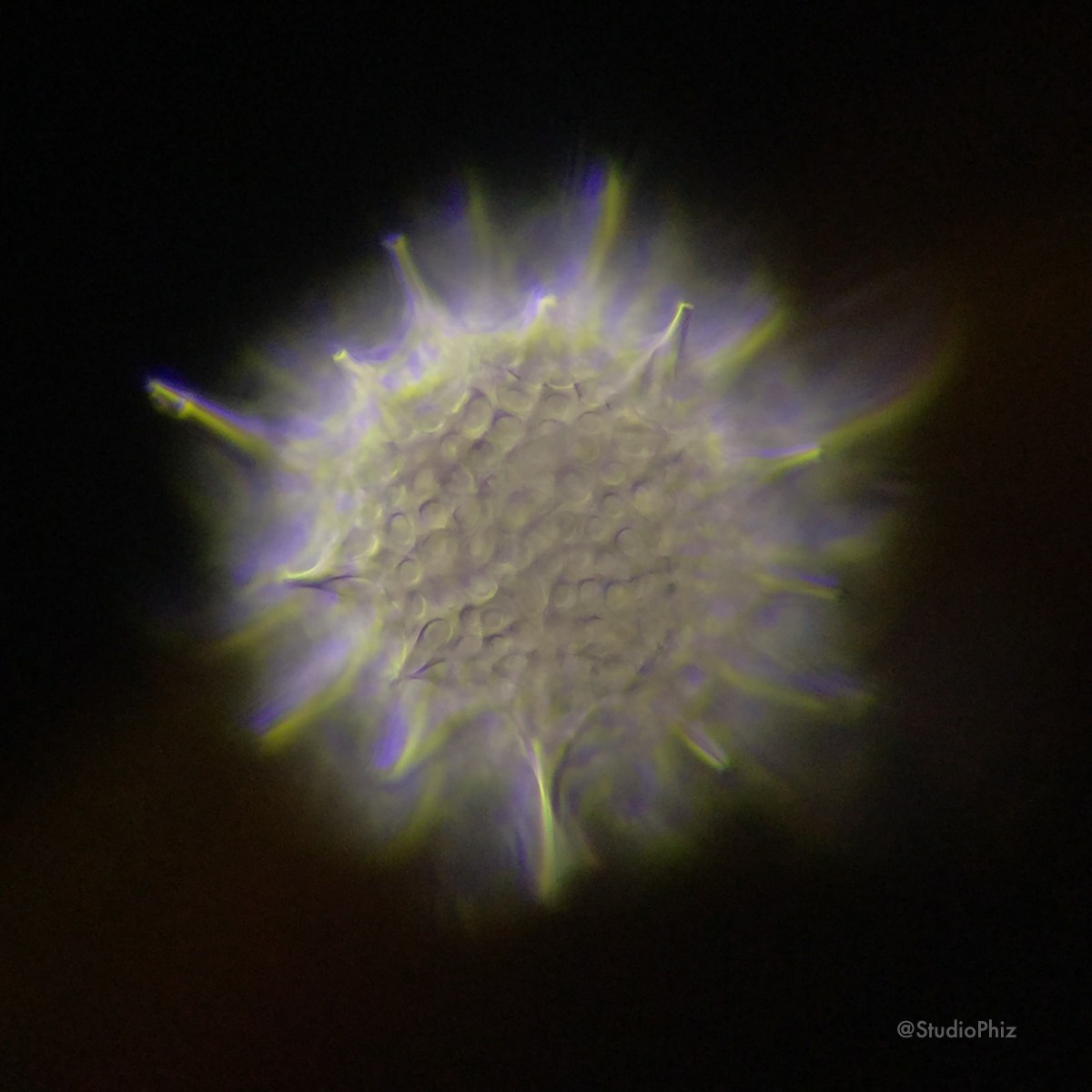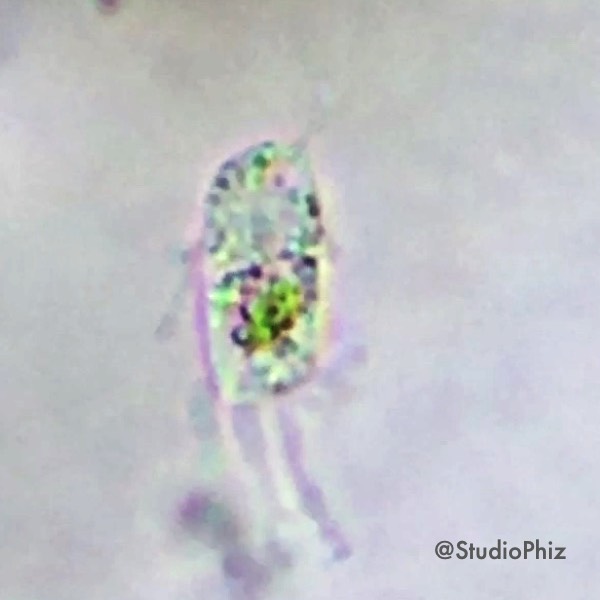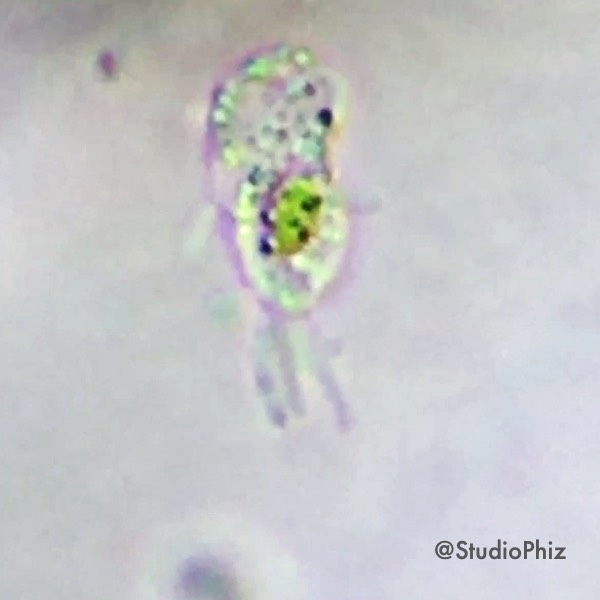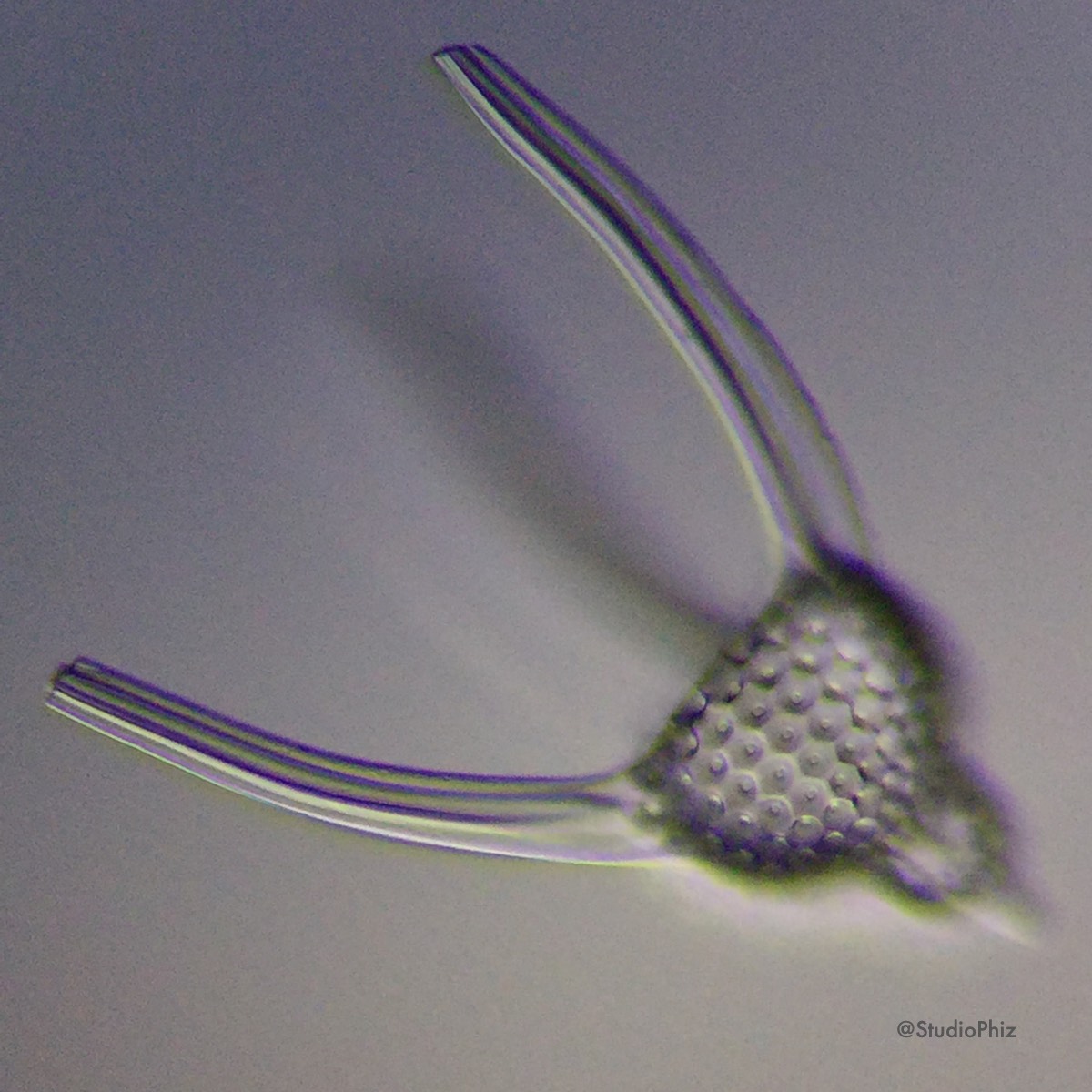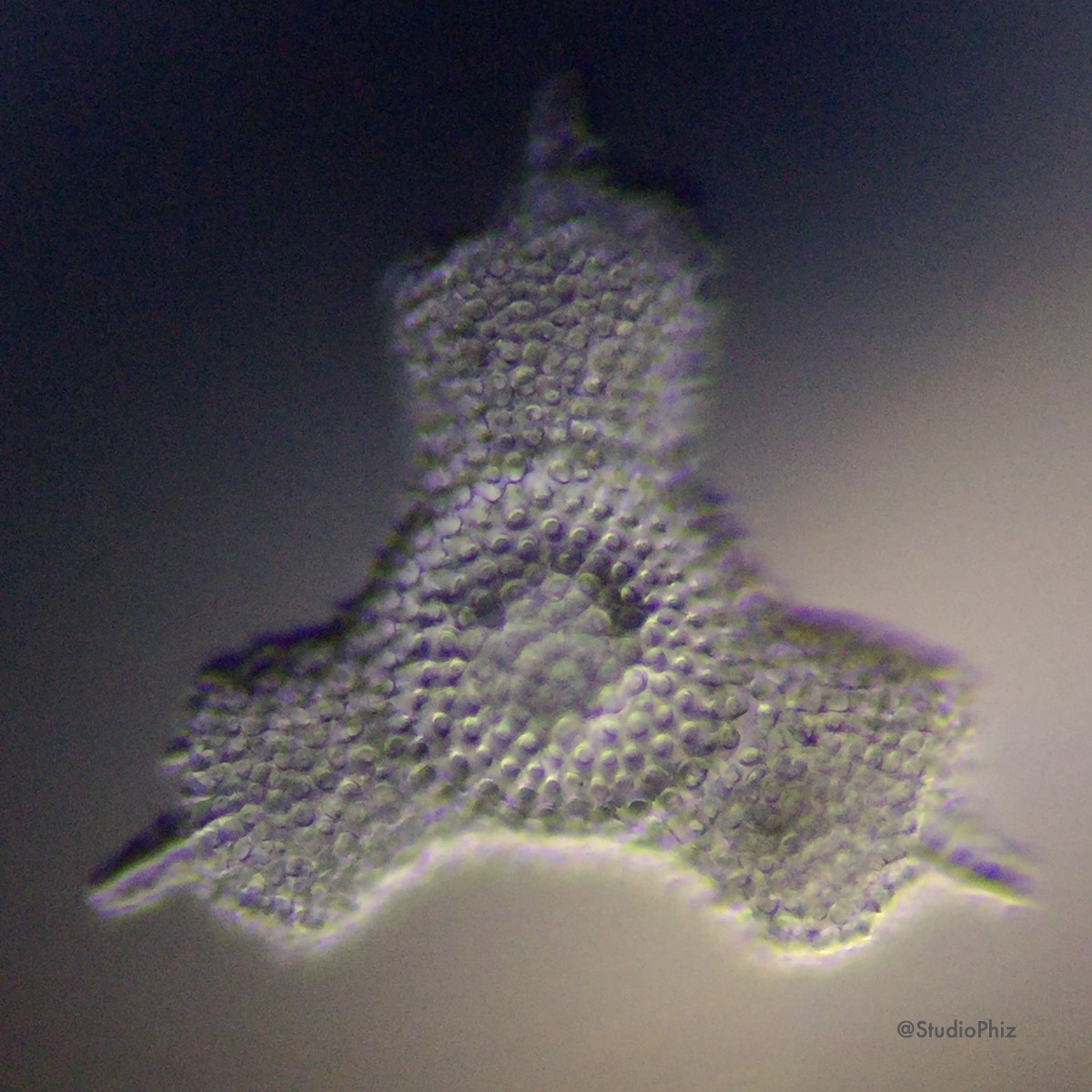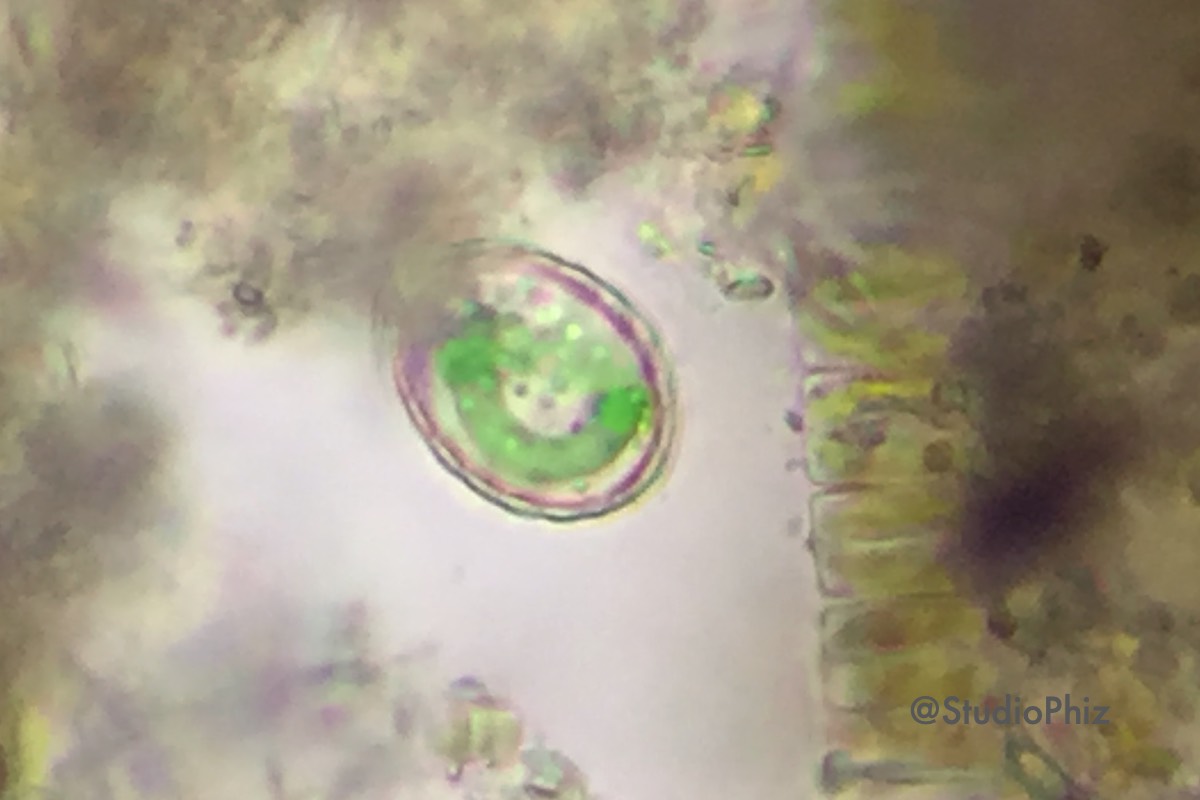こちらは不等毛類・黄金色藻の一種、マルロモナスMallomonas(ミノヒゲムシ)。
ガラス質の鱗片と棘で表面が覆われていて、長い鞭毛を使って泳ぎます。
冬が旬なのだそうです(野菜かっ!)
ちょっと宝石のペリドットを思わせる色合いですね(^^)
不等毛類というのは、元々は別の生物だったのが、進化の途中で藻類を細胞内に取り入れて藻類の仲間になった、という特徴があるのだそうです。
珪藻やコンブなどもこの仲間だそう。
面白いですね〜。
このあたりのお話に興味のある方は、こちらをどうぞ:
色素体/葉緑体の成立と多様性